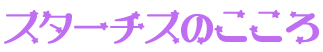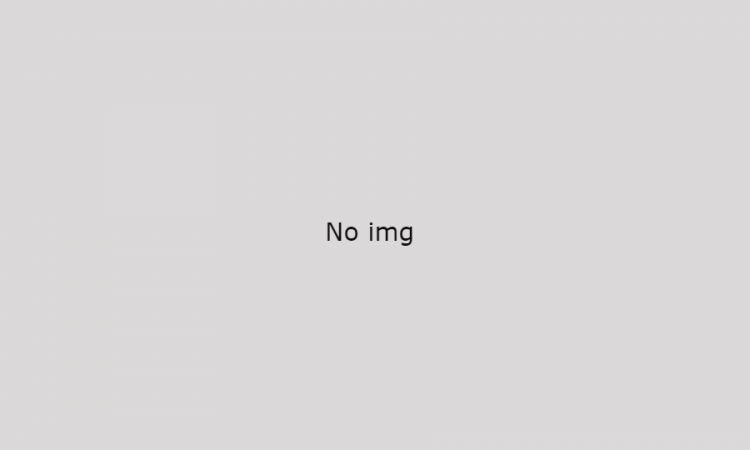健やかな成長を願って
お食い初めとは、新生児が誕生してから100日目に行う儀式です。
初めて箸を使うため、『箸揃え』や『箸初め』ともいわれています。
また、生後100日前後に祝うことから、『百日(ももか)の祝い』や『歯がため』などとも呼ばれています。
いろんな呼び名がありますが、一般的に『お食い初め』が使われます。
お食い初めは、『子供が一生、食べ物に困らない』ようにと行うものですが、生まれて100日しか経っていませんから、当然直接食べ物を与えるわけではありません。
あくまで口元に食べ物を添えるだけです。
お食い初めをするタイミング
お食い初めはピッタリ生後100日目に行わなければいけないというわけではありませんから、地域の中には生後110日目や120日目のところもあります。
大体、生後3か月~4か月頃の母乳から離乳食に変わる時期がベストといわれていますから、赤ちゃんの様子を見ながら行うと良いでしょう。
また、吉日であることが大切ですから、赤ちゃんの様子だけでなく、家族が顔を揃えられる都合の日を選びましょう。
お食い初めに必要なもの
我が子が食べ物に困らないように、そして歯が生えたことを喜ぶ行事でもありますから、お食い初めで使用する食器はすべて新しいものを用意してあげてください。
一般的に、お嫁さんの実家からお膳などを贈るのが日本のしきたりとなっていますが、最近はご自分で用意される方や、嫁ぎ先で用意される方も増えているといいます。
地域によって習わしが違いますので、それに従うのが一番でしょう。
食器の色は、性別によって異なります。
男児の場合はすべて赤色の漆器を、女児の場合は外側は黒色、内側は赤色の漆器を使用します。
ただ漆器は繊細で高価なものですから、離乳食用の食器で代用しても良いといわれています。
お食い初めで用意する献立
食器も大事ですが、献立の内容も重要です。
お食い初めは江戸時代から行われていますから、基本は一汁三菜と鯛の尾頭付を用意します。
詳しく内容を説明すると、鯛などの尾頭付の焼き魚、すまし汁、煮物、香のもの、赤飯(白飯)の5種類になります。
焼き魚は、地方によって鯛ではない場合もあります。
すまし汁は、具に鯛や鮭などの実を使用します。
そして、丈夫な歯が生えるように歯固めの小石、長生きするように梅干しを添える習慣もあります。
お食い初めのやり方は、親族の中で長寿の人から行いますが、赤ちゃんの性別によって祖父であるか祖母であるか異なります。
ですから、男の子であれば祖父、女の子であれば祖母から赤ちゃんの口に、その年の恵方に向かって食べ物を運びます。
食べ方の順番は、ご飯・汁・ご飯・魚・ご飯・汁となります。